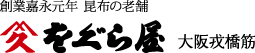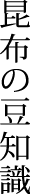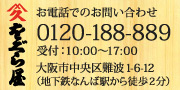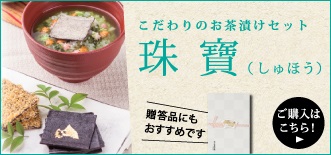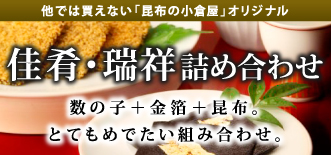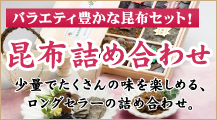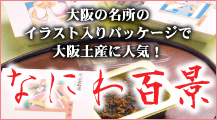「昆布の歴史」カテゴリーの記事一覧
2014.10.23
「昆布の日」っていつ?【昆布の歴史】
皆さんは「昆布の日」がいつかをご存知ですか?
日本昆布協会では、毎年11月15日を「昆布の日」として定めています。
11月15日といえば何か思い浮かぶことがありませんか?
そうです、11月15日と言えば「七五三」の日です。

この日を昆布の日として定めた理由は、七五三のお祝いに育ち盛りの子どもたちが
栄養豊富な昆布を食べて、元気に育ってほしい。
そして、昆布を食べる習慣をつけてほしいという思いから、1982年に決まりました。
またこの時期は、その年に収穫された昆布が”新昆布”として市場に出回る時期でもあり、
海からの贈り物として感謝をする気持ちも込められています。
昆布を食べる習慣が今の子どもたちの世代にも伝わってほしいですね。
2014.09.11
「昆布」=「よろこんぶ」【昆布の歴史】
昆布が古来より結婚式やおせち料理など
おめでたいことに用いられてきたことはよく知られていますが
その理由は一般に「喜ぶ」に通じるから、と言われています。
しかし、実際には「昆布」=「よろこんぶ」と言われ出したのは鎌倉・室町時代に入ってからで、
もっと古くには、昆布の古命である「ヒロメ」が「広める」に通じ、
長々としたその姿が縁起が良いと言われていたのです。
現在でも京都・大阪方面では、祝儀の際幅の広い山出し昆布をたてに二つ折りし
これをくるくる巻き、紅白の紐で結んだものを三宝にのせて床の間に飾る習慣 が残されています。
また俗に、結婚披露宴を「おひろめ」と言うのも「ヒロメ」という古称から来ているとも言われています。

戦国時代には武士階級の出陣、凱戦の儀式に昆布は欠かせぬものとなりました。
敵に「打ち勝ち喜ぶ」という語呂合せで、勝利のときには「勝ち、打ちて喜ぶ」と順序を逆にして祝いました。
当時の武士達は、戦場に赴くときも、戦に勝った時も何かにつけ昆布を食べていたのです。
これがやがて民間に伝承され、のしあわび昆布は、
結婚や元服(成人の祝い)、その他の慶事になくてはならないものになっていったのです。
2014.08.12
昆布の賞味期限は実は【昆布の歴史】
夏は食品も傷みやすい季節ですが、そう言えばみなさん昆布の賞味期限はご存知でしょうか。
本来、乾燥した出汁昆布には賞味期限が無いといわれています。
それでは実際どれくらいもつものなのかというと
実は少なくとも3年ほどは美味しくいただけるとされています。
ただし、保存の仕方を間違えてしまうとせっかくの出汁昆布が台なしになってしまいます。
これは昆布に限らず乾物全般にも言えることなのですが
保存に適した環境は、一般的に直射日光の当たらない涼しく乾燥した場所。
また湿度は大体60~67%が最適と言われています。
とは言え湿度まで細く管理するのは大変なので、乾燥剤をガラス瓶に入れて昆布を入れ、
日の当たらない棚や引き出しなどに保管するのが良いと思います。
透明なガラス瓶なら残量も確かめやすく便利です。
缶での保存は、昆布から出た塩分で缶が錆びて臭いが移ることがあるのであまりオススメはできません。
梅雨や暑い夏の時期はやはり心配だと思うので、
そんな時はチャック付きの保存袋などに入れて
空気をしっかり抜いてから冷蔵もしくは冷凍庫で保管すると安心です。
2014.07.08
「海を渡り全国を巡った昆布の道」【昆布の歴史】
鎌倉中期以降に始まり、江戸時代から明治の中期に盛んに行われた昆布の交易。
「北前船」という名の船に乗せて昆布を運んだ航路のことを『昆布ロード』と呼ぶそうです。
昆布ロードがのびて新しい土地に昆布がもたらされると、そこに独自の昆布食文化が生まれました。
たとえば大阪の昆布のつくだ煮、沖縄では野菜や豚肉といためたり、煮こんだりして食べられています。
昆布ロードは北海道から果ては沖縄まで、まさに全国を股にかけた大航路だったのです。
関東地方が全国的に見て昆布の消費量が少ないのは、昆布ロードの到達が遅かったからだとされています。
このように、私たちの食文化に欠かせない存在となった昆布の普及、
また地域による昆布の食べ方の違いは、昆布ロードの歴史的背景と深い関わりがあるのです。
2014.06.11
とろろ昆布の誕生秘話【昆布の歴史】
昆布は和食には欠かせない食材です。
つくだ煮や松前漬けとして食べるだけでなく
昆布の出汁は汁物や料理の隠し味として
多岐に渡って使われています。
そのままでも美味しい昆布を薄く削った「とろろ昆布」。
実は偶然生まれたものだったのです。
事の始まりは、電車や車も走っていない江戸時代までさかのぼります。
現在も昆布の名産地である北海道から京都へ運ぶ際、
長距離の移動によって昆布の表面にカビが生えてしまう事もしばしば。
カビを取り除く為に昆布の表面を包丁で薄く削って生まれたのが「とろろ昆布」でした。
≫小倉屋でとろろ昆布を見る